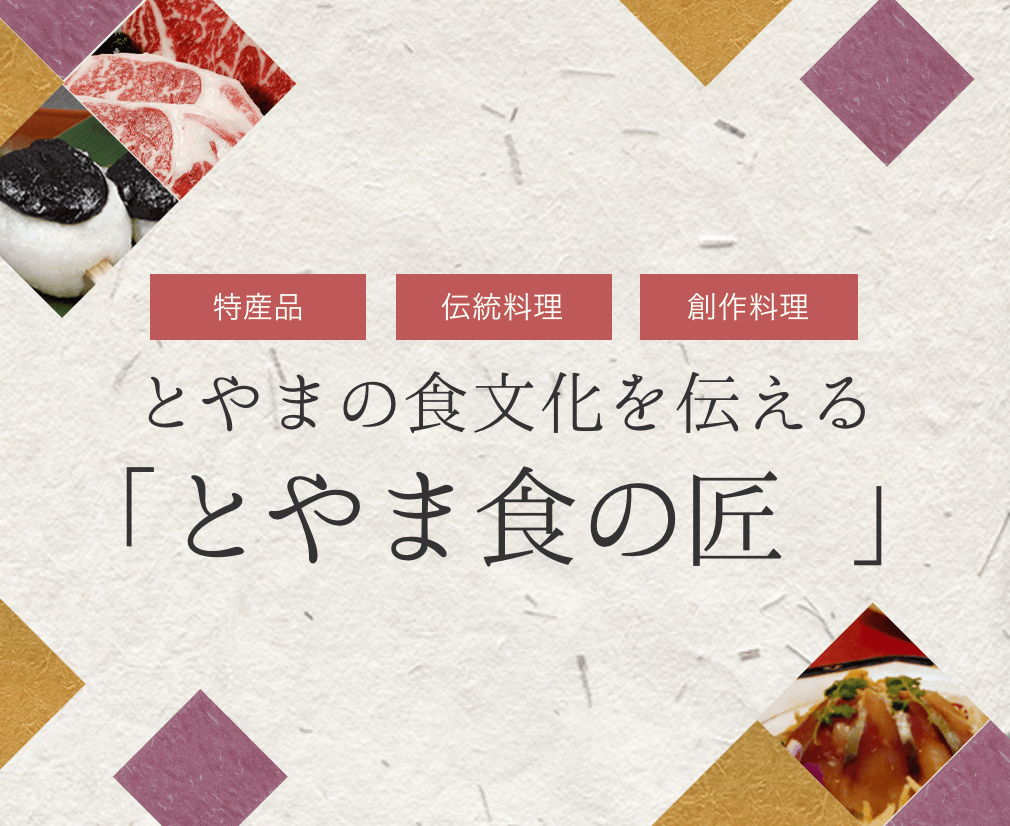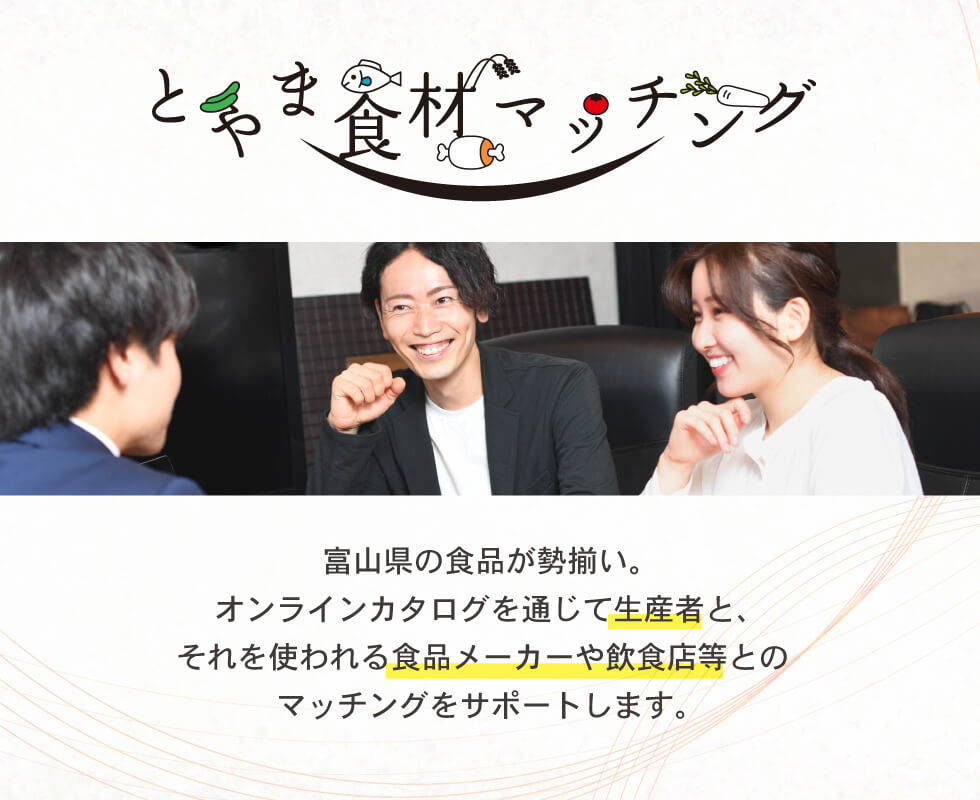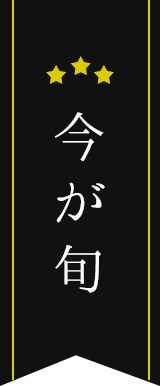ます寿し
竹の棒に曲げわっぱ。容器を締めつけるゴムをほどいて、丸い蓋をあけると、中から笹の葉が重なり合って顔を出します。その笹を開いて現れるのは、鱒は鱒でもサクラマス。鮮やかな紅色の切り身が笹の緑に映えて、見事なコントラストをつくります。富山のお土産に人気のます寿しですが、はじめて手にした時に食べ方がわからない、という人が多いのではないでしょうか。その独特の味わいとスタイルが人気を呼んで、現在は富山を代表するお土産になっており、また、富山県が認定する「富山県推奨とやまブランド」の1つです。
富山県内では、鱒寿司店の他にも、ホテルや寿司屋、惣菜店など、様々な業者がます寿しを作っています。鱒の厚みやシメ加減、酢飯の味、ご飯の炊き方、笹の葉の使い方、鱒や酢飯の盛りつけ方など、全てが同じます寿しはありません。作り手によって様々な特長が見られるのも、ます寿しの楽しみではないでしょうか。
りんご
- 旬の時期
- 8〜1月
富山県内では、加積りんご産地をモデルとして、各地で新たなりんご産地が誕生しました。平成28年度は、栽培面積(結果樹面積)94haで1,185トンが収穫されています。いずれの産地も「ふじ」栽培が主体で、年間収穫量の75%を占め11月上旬から収穫がはじまります。富山県産「ふじ」の特徴は、「高い糖度と程よい酸味」、「果汁が多くジューシー」、「シャキシャキした歯ざわりのよさ」にあり、たいへん好評を得ています。
稲積梅
- 旬の時期
- 6月
「稲積梅」は富山県の固有種の梅です。他種の梅と違いあまり枝を横に張らないのが特長で、そのため、雪が枝にたまりにくく、富山のような雪深い土地でも気候に順応してきました。
果肉はふっくらと厚くて種離れがよく、種が小さい。酸味もよいため、古くから氷見では多くの家庭で梅干しなどにされてきました。クエン酸が豊富で疲労回復に効果抜群です。
アユ
- 旬の時期
- 6~11月
アユは、その華麗に泳ぐ姿から清流の女王と称されています。
富山県では、秋に河川の中下流域で産卵し、孵化した仔魚はすぐに富山湾に降ります。冬には、沿岸から2キロ以内の範囲で、カイアシ類などの動物プランクトンを食べて成長します。
4、5月頃には河川に遡上し、夏の間に川の中上流域まで達したアユは、石に繁茂した珪藻を食べて大きく成長します。富山のアユは、一般的に8月~9月の最盛期を迎えると20cmから大きい物は30cm近くに成長します。秋には、再び下流域に入り、産卵の後、1年の生涯を終えます。
このように、一年で生涯を終えることから「年魚」、体表の粘膜にウリ科の食物のように甘くすがすがしい香りがあることから「香魚」、鱗が細かいことから「細鱗魚」と様々な呼び名があります。
ばれいしょ
- 旬の時期
- 7〜8月
平成22年度に富山県でスタートした「一億円産地づくり」は、各地のJAや地域の担ぎ手とともに、1品目1億円の大規模園芸産地づくりを目指しています。その対象品目の1つが馬鈴薯です。 この馬鈴薯生産にあたっては、全農富山県本部が購入した機械を生産者に貸し出すことで、大規模かつ効率的な生産体制を整えます。また新たに設置した野菜選別調整出荷施設に馬鈴薯を集約・選別し、さらに販売出荷も全農富山県本部が一元的に行います。
この結果、質の高い馬鈴薯を安定的に市場へ供給しブランド化を図るだけでなく、栽培農家も生産だけに専念することができます。平成30年は県内の9JA管内で取り組み、作付面積が13haとなっております。
現在は、「男爵」を中心に収穫時期の異なる3種の品種を組み合わせて生産しています。それにより、長い期間にわたって出荷ができ、安定供給にもつながっています。
生産高が増えたことで、これまで中心だった県内量販店への出荷から県内外の外食・中食産業・加工業務向けの出荷も増えてきています。コロッケの消費量が日本一の富山で、県産馬鈴薯を使ったコロッケを口にする機会が今後ますます多くなりそうです。
バイガイ
- 旬の時期
- 通年
富山湾ではオオエッチュウバイ、カガバイ、ツバイ、チヂミエゾボラ(エゾバラモドキ)の4種類のバイガイが水揚げされます。4種類ものバイガイがとれるのは全国でも珍しいです。
地元ではチヂミエゾボラがもっとも大きく高価で、次いでオオエッチュウバイ、カガバイ、ツバイの順に大きいです。
ツバイは、漁獲量も多く、殻の頭頂部が黒いことから「ケツグロ」とも呼ばれています。